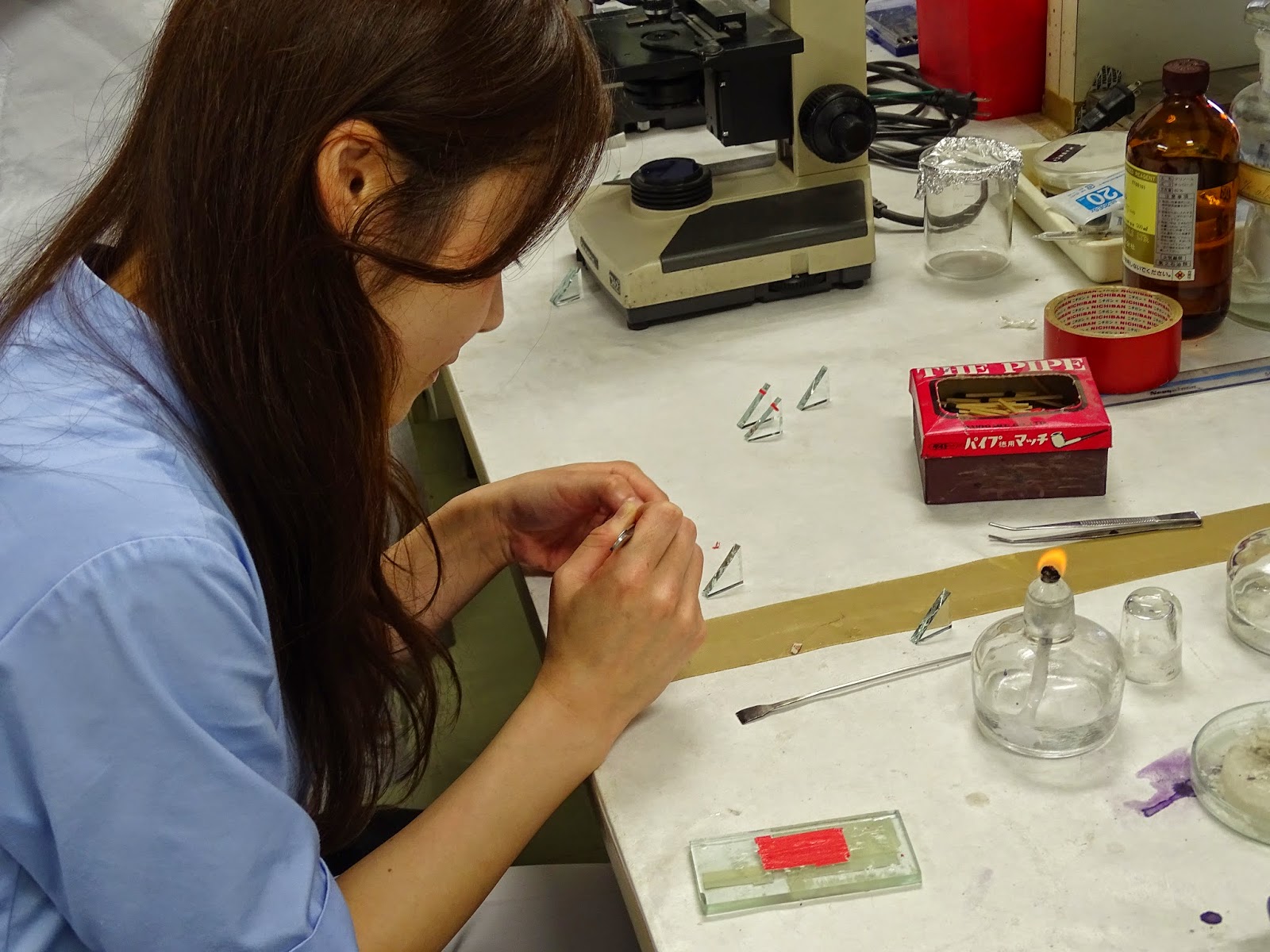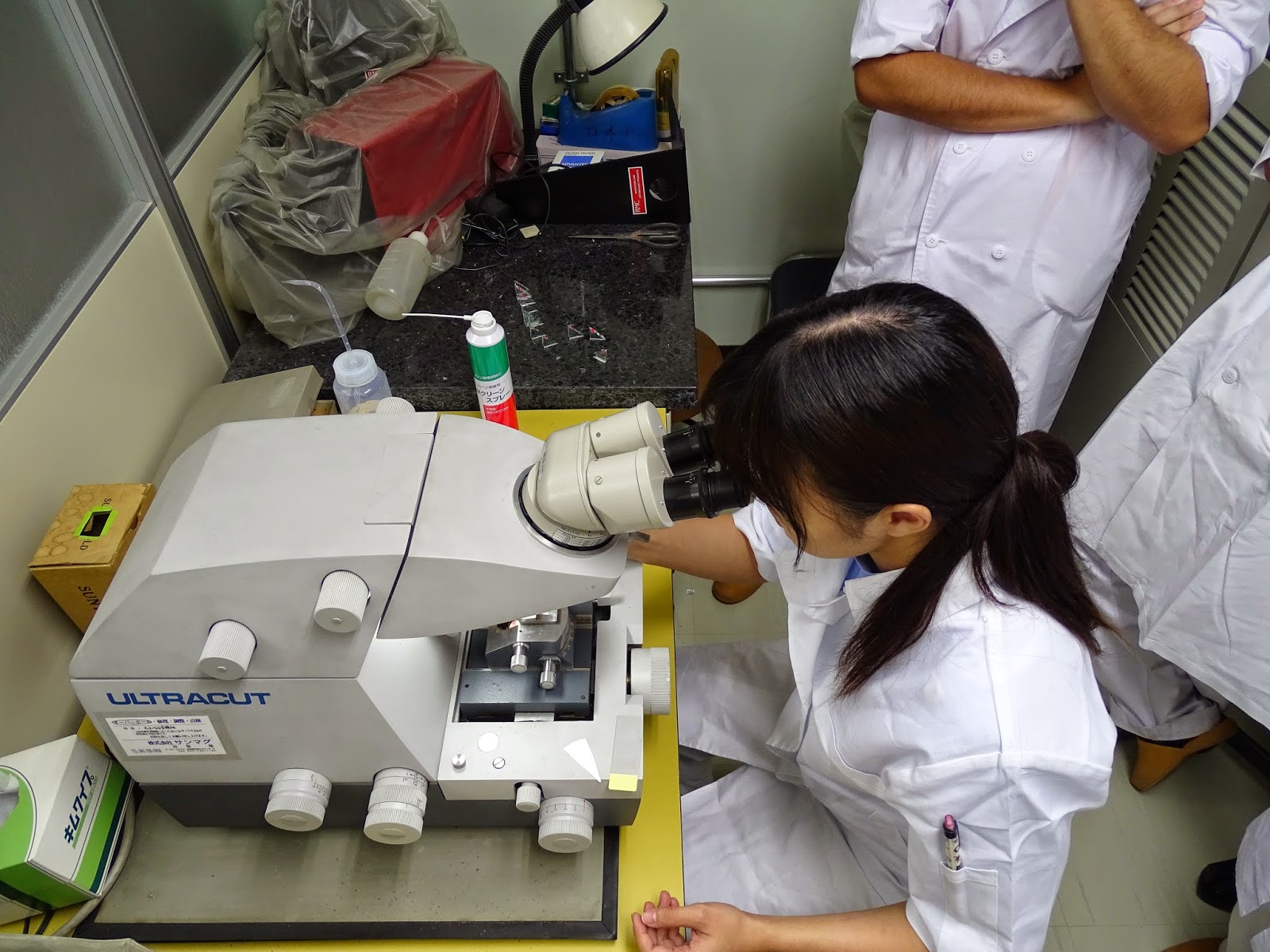レポーターは楠瀬隆生先生(生物学)。
イントロダクションでは糸をつくるの体のつくり,面白い習性,網を張らない仲間などクモの世界の多様性が紹介されました。
投げ縄グモの話題になり,粘球をつけた糸(投げ縄)の正体は何か,フェロモン臭を利用してオスのガをとるらしい,など興味深い話が続きます。
そして,いよいよ今回の発見が紹介されました。
これが貴重な日本の投げ縄グモ「ムツトゲイセキグモ」。
コガネグモ科 Ordgarius sexspinosus
南方系で体長は1.2cmほどの小さなクモ。昼間は葉の裏などでじっと動かず餌は夜にとるので発見が難しい。
発見者は海老原智康先生(総合歯科診療学)。「これは......!」と楠瀬隆生先生の所へ持ち込み,調べた結果「やはり........!」と判断されたそうです。
発表後も質問は続き,楽しいデスカッションになりました。
クモの世界は奥が深く,次の機会も期待できます。