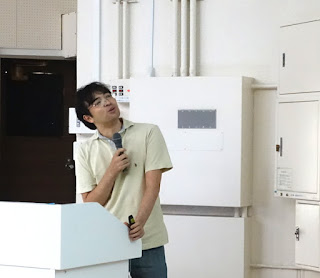本年度(2015年10月から2016年9月まで)は46名の尊いご献体があり,解剖学の礎(いしずえ)となられました。ご冥福をお祈りいたします。
ご遺族ならびに教職員の焼香の後,両学部学生代表が焼香します。(写真は松戸歯学部の学生代表)。
読経の中,両学部学生(2年次生)の焼香が続きます。
講話をいただき(写真),続いて歯学部解剖学講座から挨拶があり実習の様子も話されました。
解剖実習は既に10月から始められています。
今日を転機にさらなる勉強に励まれますように。
(私の解剖体法要への参列は今回で終わります。
感謝いたします。)
(私の解剖体法要への参列は今回で終わります。
感謝いたします。)
************************
築地から銀座へ。地下鉄銀座駅の出口は海面から4mの高さ。一瞬,足元から不安が登ってきました。
銀座は週末のにぎわい。
今年は”ハロウィン”があちこちで話題になっています。